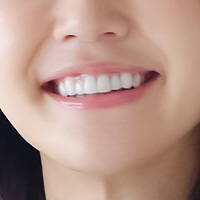歯茎の痛み・腫れ・出血は歯周病のサイン?
原因と治療法を専門医が徹底解説
症状から記事を探す
「歯を磨くと血が出る」「歯茎が赤く腫れて痛い」「何もしていないのにズキズキする」 このような歯茎の不快な症状に、不安を感じていませんか?
その痛みや腫れは、単なる一時的な口内炎や疲れのせいだと自己判断してしまうのは大変危険です。
実は、それらの症状の多くが、日本人の成人の約8割が罹患していると言われる「歯周病」の危険なサインである可能性があります。
歯周病は、初期段階では自覚症状がほとんどなく進行するため「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれる病気です。
痛みを感じ始めたときには、すでに病状がかなり進行しているケースも少なくありません。
放置すれば、歯を支える骨が溶けて歯が抜け落ちるだけでなく、糖尿病や心筋梗塞、認知症といった全身の深刻な疾患のリスクを高めることも明らかになっています。
この記事では、歯茎の痛みに悩む方へ向けて、考えられる原因からご自身でできる応急処置、放置するリスク、そして最新の歯科治療までを専門家の視点から網羅的に解説します。
大切な歯と全身の健康を守るため、まずはご自身の症状と正しく向き合うことから始めましょう。
目次
01.歯茎の痛みとは?その危険なサインを見逃さないで
02.なぜ歯茎は痛むのか?考えられる主な原因
03.歯科医院を受診するまでの応急処置とNG行動
04.放置は危険!歯茎の痛みと歯周病がもたらす深刻なリスク
05.歯茎の痛みで東戸塚エス歯科クリニックが選ばれる理由
06.当院の精密歯周病治療の流れ
07.歯茎の痛みに関するよくあるご質問
歯茎の痛みとは?その危険なサインを見逃さないで
歯茎の痛みとは、歯肉(歯茎)に何らかの異常が起き、炎症反応が起きていることを知らせる身体からの警告信号です。
痛みだけでなく、以下のような症状を伴う場合は特に注意が必要です。
これらのサインは、お口の中のトラブルが進行している可能性を示唆しています。
歯茎が赤く腫れる、ぶよぶよする
健康な歯茎は引き締まったピンク色をしていますが、炎症が起きると赤く腫れあがり、締まりのない状態になります。
ブラッシング時の出血
歯ブラシを当てただけで簡単に出血するのは、歯肉炎の典型的な症状です。
健康な歯茎から頻繁に出血することはありません。
歯が浮いたような感じがする
歯を支える組織に炎症が広がると、歯が浮いたような違和感を覚えることがあります。
口臭が強くなる
歯周病菌が作り出すガスにより、独特の不快な口臭が発生します。
歯茎から膿が出る
歯と歯茎の溝(歯周ポケット)で細菌が増殖し、炎症が強くなると、指で押した際に膿が出てくることがあります。
何もしなくてもズキズキ痛む
刺激がないのに拍動するような強い痛みがある場合、炎症が急性化しているか、歯の根の先に膿が溜まっている可能性があります。
歯が長くなったように見える・歯と歯の間に隙間ができた
歯周病によって歯茎が下がる(歯肉退縮)と、歯の根元が露出し、歯が長く見えたり、隙間が目立ったりします。
歯がグラグラする
歯を支える骨が溶かされているサインであり、歯周病がかなり進行していることを示します。
これらの症状に一つでも心当たりがあれば、それは身体が発するSOSです。
決して軽視せず、できるだけ早く専門家である歯科医師に相談することが重要です。
なぜ歯茎は痛むのか?考えられる主な原因
歯茎の痛みを引き起こす原因は一つではありません。
原因を正確に特定することが、適切な治療への第一歩となります。
最も一般的な原因「歯周病(歯肉炎・歯周炎)」
歯茎の痛みの最大の原因は、歯周病です。
歯周病は、プラーク(歯垢)に含まれる細菌によって引き起こされる炎症性疾患で、進行段階によって「歯肉炎」と「歯周炎」に分けられます。
歯肉炎
歯周病の初期段階で、炎症が歯茎に限定されている状態です。
主な症状は歯茎の赤み、腫れ、ブラッシング時の出血などです。
この段階では、まだ歯を支える骨に影響はありません。
歯周炎
歯肉炎が進行し、炎症が歯を支える顎の骨(歯槽骨)や歯根膜にまで及んだ状態です。
歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)が深くなり、骨が溶かされ始めます。
進行すると歯がグラグラになり、最終的には歯が抜け落ちてしまいます。
一度溶けてしまった骨は、基本的には元に戻りません。
親知らずのトラブル(智歯周囲炎)
親知らずが斜めや横向きに生えている場合、歯と歯茎の間に汚れが溜まり、細菌が繁殖して炎症を起こすと、「智歯周囲炎」となり、奥の歯茎に強い痛みや腫れを引き起こします。
体調が悪い時などに再発しやすいのが特徴です。
歯の根の先の炎症(根尖性歯周炎)
進行した虫歯を放置したり、過去に受けた根管治療が不十分だったりすると、歯の根の先端から細菌が顎の骨に広がり、膿の袋(根尖病巣)を作ることがあります。
これが急性化すると、歯茎が大きく腫れて激しく痛みます。
歯茎に「おでき」(フィステル)のようなものができることもあります。
その他の原因
歯の破折・ひび(マイクロクラック)
歯ぎしりや食いしばりなどで歯にひびが入ると、そこから細菌が侵入し、歯茎に炎症を起こして痛むことがあります。
口内炎
白い小さな潰瘍ができるアフタ性口内炎が歯茎にできると、強い痛みを伴います。
物理的な傷
硬い歯ブラシでゴシゴシ磨きすぎたり、硬い食べ物が刺さったりして歯茎が傷つき、痛むこともあります。
不適合な被せ物・入れ歯
被せ物や入れ歯の縁が歯茎に合っていないと、常に刺激が加わり、慢性的な炎症や痛みの原因になります。
ホルモンバランスの変化
特に女性の場合、妊娠・出産期や更年期など、ホルモンバランスが大きく変動する時期は、特定の歯周病菌が活発になり、「妊娠性歯肉炎」などを起こしやすくなります。
このように、歯茎の痛みの原因は多岐にわたります。
自己判断はせず、正確な原因を特定するために、必ず歯科医院で診察を受けましょう。
歯科医院を受診するまでの応急処置とNG行動
突然の歯茎の痛みで、すぐに歯科医院に行けない場合もあるでしょう。
ここでは、痛みを一時的に和らげるための応急処置と、症状を悪化させる可能性のあるNG行動について解説します。
これらはあくまで一時的な対処法であり、根本的な解決にはならないことをご理解ください。
自宅でできる応急処置
痛み止め(鎮痛剤)の服用
市販の鎮痛剤(ロキソプロフェンやイブプロフェンを含むもの)は、痛みを抑えるのに効果的です。
必ず用法・用量を守って服用してください。
患部を冷やす
痛む側の頬の外側から、濡れタオルやタオルで包んだ保冷剤を当てて冷やすと、血流が穏やかになり痛みが和らぐ効果が期待できます。
ただし、氷などを直接口に含んで冷やすと、強い刺激でかえって痛みが増すことがあるため避けてください。
ぬるま湯で優しくうがいをする
口の中に食べかすなどが詰まって痛みを引き起こしている場合、ぬるま湯で優しくうがいをすることで洗い流せる場合があります。
安静にする
身体が疲れていると免疫力が低下し、炎症が悪化しやすくなります。
できるだけ体を休め、安静に過ごしましょう。
症状を悪化させるNG行動
飲酒や長時間の入浴、激しい運動
これらは血行を促進する行為です。
血流が良くなると、炎症を起こしている部分の神経が圧迫され、痛みがさらに強くなる可能性があります。
喫煙
タバコは血流を阻害し、歯茎の免疫力を低下させます。
また、傷の治りを遅らせる原因にもなるため、喫煙は避けるべきです。
患部を指や舌で触る
気になるからといって、痛む場所を頻繁に触ると、細菌が入り込んだり、刺激で炎症が悪化したりする恐れがあります。
放置は危険!歯茎の痛みと歯周病がもたらす深刻なリスク
「たまに血が出るだけ」「痛みが治まったから大丈夫」と歯茎からのサインを無視し続けると、お口の中だけでなく、全身の健康にまで深刻な影響が及ぶ可能性があります。
お口の中で起こるリスク
歯を失う
歯周病を放置した場合の最も悲しい結末は、歯を失うことです。
歯周病は、日本人が歯を失う原因の第1位であり、虫歯よりも多くの歯が歯周病によって失われています。
歯茎が下がり、見た目が悪くなる
歯周病で歯茎が下がると、歯が長く見えたり、歯の根元が露出して黒い隙間(ブラックトライングル)ができたりと、見た目の美しさが損なわれます。
口臭の悪化
歯周ポケット内で増殖した細菌が発する硫化水素などのガスにより、周囲の人に不快感を与えるほどの強い口臭が発生します。
治療が困難・高額になる
症状が進行すればするほど、治療は複雑になり、期間も費用も増大します。
骨を失ってしまった場合、インプラント治療などを行うにも骨造成といった追加の処置が必要になることがあります。
全身の健康を脅かすリスク
歯周病は、お口の中だけの病気ではありません。
近年の研究で、歯周病菌や炎症によって生じる物質が、歯茎の血管から血流に乗って全身を巡り、様々な病気を引き起こしたり、悪化させたりすることが分かってきました。
糖尿病
歯周病は「糖尿病の第6の合併症」とも呼ばれ、相互に悪影響を及ぼします。
歯周病の慢性的な炎症は、血糖値を下げるインスリンの働きを阻害し、血糖コントロールを困難にします。
心血管疾患(心筋梗塞・脳梗塞)
歯周病菌が血流に入り、血管の壁に付着すると、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めます。
誤嚥性肺炎
特に高齢者において、歯周病菌を含む唾液が誤って気管や肺に入ることで起こる肺炎です。
妊娠トラブル
妊娠中の女性が歯周病にかかっていると、血中の炎症物質が子宮の収縮を促し、早産や低体重児出産のリスクが高まることが報告されています。
認知症・がん
最新の研究では、歯周病菌がアルツハイマー型認知症の原因物質の蓄積を促進する可能性や、特定のがんのリスクを高める可能性も指摘されています。
歯茎の痛みを放置することは、将来の健康に対する大きな負債を抱えることと同じです。
早期発見・早期治療が、あなたの大切な歯と身体を守るための鍵となります。
歯茎の痛みで東戸塚エス歯科クリニックが選ばれる理由
歯茎の痛みや歯周病の治療は、どの歯科医院で受けても同じではありません。
原因を正確に突き止め、再発を防ぎ、長期的に安定した口腔環境を維持するためには、高度な診断能力と精密な治療技術が不可欠です。
東戸塚エス歯科クリニックが、多くの患者様に選ばれている理由がここにあります。
理由1:原因を徹底的に特定する「精密診断体制」
的確な治療は、的確な診断から始まります。当院では、経験や勘だけに頼るのではなく、先進的な医療機器を駆使した客観的なデータに基づき、痛みの根本原因を徹底的に追求します。
歯科用CTによる3次元分析
通常のレントゲンでは見えない顎の骨の吸収状態や、歯の根の先の病巣などを3次元の立体画像で詳細に把握します。
これにより、歯周病の進行度をより正確に診断し、安全な治療計画を立案できます。
位相差顕微鏡による細菌検査
患者様のお口から採取したプラークをその場で位相差顕微鏡で観察し、どのような種類の歯周病菌が、どのくらい活動しているのかをリアルタイムで確認します。
原因菌を「見える化」することで、患者様ご自身の病状への理解を深め、より効果的な治療法を選択することが可能です。
理由2:歯を長期的に守る「科学的根拠に基づく精密治療」
当院の理念は、治療した歯が「その歯にとって最後の治療」となることです。
その場しのぎの対症療法ではなく、歯の寿命を最大限に延ばすための精密治療を提供します。
マイクロスコープの活用
歯周外科治療や複雑な歯石除去において、肉眼の最大20倍以上に視野を拡大できる歯科用マイクロスコープ(カールツァイス社製)を使用します。
これにより、感染源の取り残しを防ぎ、健康な組織へのダメージを最小限に抑えた、極めて精度の高い治療を実現します。
専門医による包括的アプローチ
当院には、日本歯周病学会に所属するドクターや、国内外の著名な研修プログラムを修了したドクターが在籍しています。
歯周病治療はもちろんのこと、お口全体を一つの単位として捉えた包括的な治療を提供します。
歯周病によって失われた歯を補うインプラント治療や、歯並びの乱れが歯周病の原因となっている場合の矯正治療など、各分野の専門家が連携して最適な治療計画を立案します。
理由3:再発を防ぐ「徹底したメンテナンスプログラム」
歯周病は、一度治療が終われば完治するというものではなく、継続的な管理が必要な慢性疾患です。
当院では、治療後の良好な状態を維持し、再発を徹底的に防ぐためのメンテナンスプログラムに力を入れています。
担当歯科衛生士制
専門的なトレーニングを受けた歯科衛生士が、患者様一人ひとりのお口の状態に合わせたオーダーメイドのケアを提供します。
PMTC(専門的機械的歯面清掃)
毎日の歯磨きでは落としきれない細菌の塊「バイオフィルム」を、専用の機器を用いて徹底的に破壊・除去し、歯周病の再発リスクを低減します。
当院の精密歯周病治療の流れ
当院では、患者様に安心して治療を受けていただくため、丁寧な説明と同意(インフォームド・コンセント)を徹底しています。
治療の全体像をご理解いただいた上で、二人三脚でゴールを目指します。
STEP1:初診・カウンセリング
まず、患者様が抱えているお悩みや不安、治療に対するご希望などを詳しくお伺いします。
どんな些細なことでも、気兼ねなくお話しください。
STEP2:精密検査
現在の状態を正確に把握するため、各種検査を行います。
・歯周ポケット検査
・レントゲン・歯科用CT撮影
・口腔内写真撮影
・位相差顕微鏡による細菌検査
STEP3:治療計画の立案とご説明
検査結果を基に、現在の歯周病の進行段階、考えられる治療法の選択肢、それぞれのメリット・デメリット、期間、費用などを分かりやすくご説明します。
患者様にご納得いただけるまで、丁寧に対話を重ねます。
STEP4:歯周基本治療
治療計画にご同意いただけましたら、治療を開始します。
まずは、歯周病の根本原因であるプラークや歯石を取り除く基本治療を行います。
・ブラッシング指導(TBI)
・スケーリング(歯石除去)
・ルートプレーニング(SRP:歯根面の滑沢化)
STEP5:再評価検査
基本治療によって歯茎の状態がどの程度改善したかを再度検査し、評価します。
多くの場合、初期の歯肉炎はこの段階で大幅に改善します。
STEP6:歯周外科治療(必要な場合)
基本治療を行っても深い歯周ポケットが残っているなど、改善が見られない場合には、歯周外科治療をご提案することがあります。
歯茎を切開し、歯根の深い部分に付着した歯石を直接見て取り除くフラップ手術などを行います。
STEP7:メンテナンス
治療によって得られた健康な状態を維持するため、3~6ヶ月に一度の定期的なメンテナンスに移行します。
専門家によるクリーニングとチェックを継続することが、再発防止の鍵となります。
歯茎の痛みに関するよくあるご質問
Q1. 歯茎が痛いとき、市販の痛み止めを飲んでも大丈夫ですか?
A1. はい、急な痛みに対する一時的な応急処置として、市販の鎮痛剤を服用することは有効です。
ただし、これは痛みを一時的に感じなくさせているだけで、原因そのものが治ったわけではありません。
薬が効いている間に、必ず歯科医院を受診してください。
Q2. 歯磨きのたびに血が出ます。強く磨きすぎでしょうか?
A2. 歯茎からの出血は、歯肉炎の最も代表的なサインです。
力任せのブラッシングは歯茎を傷つける原因になりますが、出血を恐れて歯磨きが不十分になると、さらにプラークが溜まって炎症が悪化するという悪循環に陥ります。
一度、歯科医院でご自身に合った正しいブラッシング方法の指導を受けることを強くお勧めします。
Q3. 歯周病の治療は痛いですか?
A3. 歯石を取る際などに多少の痛みや違和感を伴うことがありますが、必要に応じて麻酔を使用しますので、ほとんど痛みを感じることなく治療を受けられます。
当院では、患者様の負担を最小限にするため、表面麻酔を用いるなど無痛治療にも配慮しておりますので、ご安心ください。
Q4. 歯周病は完全に治りますか?
A4. 歯周病は、高血圧や糖尿病と同じように「慢性疾患」と位置づけられています。
治療によって炎症を抑え、進行を食い止めることは可能ですが、一度溶けてしまった骨を完全に元通りにすることは困難です。
そのため、治療後も再発させないための定期的なメンテナンスが非常に重要になります。
Q5. 治療には何回くらい通う必要がありますか?
A5. 歯周病の進行度によって大きく異なります。
初期の歯肉炎であれば、数回の通院で改善が見込めます。
歯周炎にまで進行している場合は、歯周基本治療、再評価、そしてメンテナンスと、治療期間は数ヶ月から年単位になることもあります。
Q6. 歯周病治療の費用はどのくらいかかりますか?
A6. 歯周基本治療(検査、歯石除去、ブラッシング指導など)は、基本的にすべて健康保険の適用範囲内で行われます。
歯周外科治療や、失われた骨を再生させる歯周組織再生療法など、より高度な治療に関しては自費診療となる場合があります。
詳細はカウンセリングの際に詳しくご説明いたします。
Q7. 歯石を取ったら歯がしみるようになりました。
A7. 歯の根元を厚く覆っていた歯石がなくなることで、今まで隠れていた歯の根の部分が露出し、一時的にしみやすくなることがあります。
これは異常なことではなく、多くの場合、時間の経過とともに徐々に落ち着いていきます。
Q8. 妊娠中でも歯周病治療は受けられますか?
A8. はい、比較的体調の安定する妊娠中期(安定期)であれば、問題なく治療を受けられます。
妊娠中はホルモンバランスの変化により「妊娠性歯肉炎」と呼ばれる状態になりやすく、歯周病が悪化しやすい時期でもあります。
むしろ、お腹の赤ちゃんのためにも、積極的な口腔ケアが推奨されます。
Q9. 歯周病はうつりますか?
A9. 歯周病は細菌による感染症なので、夫婦間や親子間でのキスや食器の共有などによって、原因菌がうつる(伝播する)可能性はあります。
ただし、菌がうつったからといって必ず発症するわけではなく、その人の歯磨きの習慣や生活習慣、免疫力などが大きく関わってきます。
Q10. 歯茎が下がって歯が長く見えます。元に戻すことはできますか?
A10. はい、「歯周形成外科」という専門的な治療法を用いることで、下がってしまった歯茎を回復させ、見た目を改善できる場合があります。
歯周病の進行を完全にコントロールした上で、結合組織移植術などの方法で歯茎の再生を図ります。
当院では審美歯科にも力を入れていますので 、ご興味のある方はご相談ください。
Q11. タバコは歯周病に悪いと聞きましたが、本当ですか?
A11. はい、本当です。
喫煙は歯周病の最大のリスクファクターの一つです。
タバコに含まれるニコチンが血管を収縮させ、歯茎の血流を悪化させます。
これにより、歯茎の抵抗力が弱まり、歯周病が進行しやすくなるだけでなく、治療を行っても非常に治りにくくなります。